| 漆器 |
木曽漆器の始まりについては、今から600年程前にさかのぼります。木曽福島町八沢(昔は富田町と呼ばれていました。)に、竜源寺というお寺があります。そのお寺にある経箱(お経を入れておく箱)は、漆塗りでできており、経箱の裏に「応永元年」の年号と作った人の名前が書かれていることから、この頃には、もうすでに漆塗りが行われていたということになります。
また、江戸時代の領主「山村甚兵衛」のもとで、木曽檜の利用が許されており(檜は漆器の木地として使用していました)、京都・大阪・江戸を旅する人たちにとって、おみやげ品として人気があり、日本中に木曽の工芸品は広まっていきました。
|
| 漆 |
| 漆とは、漆科植物から採った樹液(木から採れた汁)です。塗料または接着剤となる物資で、東洋独特の植物です。 塗料として世界で最初に使用されたのは、今から四千年も前の中国と言われています。日本では縄文時代の土器から、漆を使用したものが沢山発見されています。国産漆は、産出量は少ないですが品質はとても良く、主な産地は、青森・岩手・秋田・石川・長野・岐阜・福井・新潟・千葉・茨城県などです。 漆の良い点は、塗料として酸やアルカリに強く、また高温・低温などにも強い物です。電気も通しにくく、紫外線・赤外線に対する抵抗力も、他の人工塗料よりすぐれ、接着剤としても大変すぐれた性質を持っています。 |
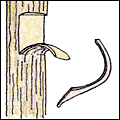 |
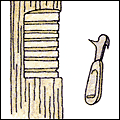 |
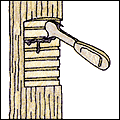 |
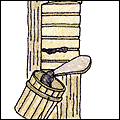 |
| ・漆の液を採るために、木に傷を付ける所を決め、皮剥(曲)で表面の皮を削り取ります。 | ・掻き傷を掻鎌という道具を使って、6~8mmくらいの間をあけて、平行に傷をつけます。 | ・掻鎌と一緒に付いている鋭利尖刀で、傷の中心を深く突き切ると漆の液がしみ出てきます。 | ・漆の液がしみ出てきたところを、鉄製の掻ヘラで掻き取り、受筒(漆壺・合筒)に採り入れます。 |